NEW
ずっと茅ヶ崎で暮らしたい
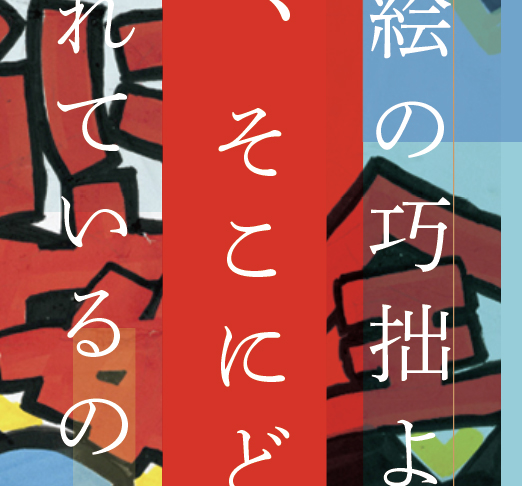
「自転車のまち」を守るステッカー
市内の路上でしばしば見かける「自転車止まれ」のステッカー。
児童が描いたと思しき愛らしい絵柄を目にした人も少なくないと思うが、じつはこれ、市が策定する「第2次ちがさき自転車プラン」に基づいて行われたもの。何でも茅ヶ崎は自転車利用率が高いぶん自転車関連の事故も多く、全事故に占める自転車事故の割合が県平均を上回るのだとか。
そうした状況を改善すべく、自転車の安全利用を呼びかけるために行われたのがこの「自転車止まれ」ステッカー大作戦。可愛い絵柄ゆえつい微笑ましい気持ちが先に来るが、本来の目的はあくまで「啓発」であることを忘れてはいけない。
というわけで、今回改めて「自転車止まれ」ステッカーをシゲシゲと見た。デザインは4種類、描いたのは市内小学校に通う4年生。ステッカーは小学生自身が危険だと気づいた交差点に設置されたというが、この「本人自らが気づいた」という点が何より大事。想像や思いつきではない、体験に紐づいた発想は理屈抜きに強いからだ。
例えば4枚のステッカーの中に、「ブレーキが守る自分の命」の標語とともに、自転車のグリップとブレーキ部分が描かれたものがある。描き手は幼い頃、目の前で自転車事故を目撃したという。そのショックからブレーキや一時停止位の重要性を思い知らされ、ブレーキ部分をクローズアップして描くことを思いついた。 交通安全の絵柄としては珍しいかもしれないが、それだけに思わずハッとさせられる。当たり前に感じていたブレーキの重要性を再認識させられる。それがきっかけとなって「一時停止しよう」「ブレーキを点検しよう」との注意喚起が促され、事故の減少につながったとすれば、それはほかでもない「体験が生んだ表現」のお手柄と言えるのではないか。
幼児教育の専門家から聞いた話だが、小学校受験の必須科目である絵画では、絵の巧拙よりなぜその絵を描いたか、そこにどのような思いが込められているのかなど「体験を伝えること」が重視されるという。そのため幼児教室では「感性」より、「体験」をよりわかりやすく、効果的に伝えるための技術を優先的に指導する。するとどの子も次第に上手に描けるようになり、絵を描くことが楽しくなり、より腕を上げるという例が多いのだそう。
「堅苦しいこと言わず、子どもには感性で自由に描かせてあげてよ」とも思うけれど、自己の「体験」や「思い」を意識するのに早すぎることはない。指導が呼び水となって感性が花開くこともないとは言えない。「絵は生まれながらの感性」というのは、ひょっとすると単なるの思い込みに過ぎないかもしれない。
ただ、個人的にはやたら技巧的な絵は好きになれない。小学生の描いた「自転車止まれ」ステッカーを見てつくづく思う。忘れられない体験を自分なりにすくい上げ、伝えたい思いを込められるか。例えば「人の命を救えたら」「事故を一つでもなくせたら」という願いが込められるかどうか。
それは誰しもの中にある祈りであり、体験を表現するとは祈るということなのかもしれない。

藤原千尋
ふじわらちひろ/1967年東京生まれ、2006年より茅ヶ崎市松が丘在住/出版社勤務を経て単行本ライター。ビジネス、教育、社会貢献、生き方老い方など幅広いジャンルの企画とライティングを手がける。















